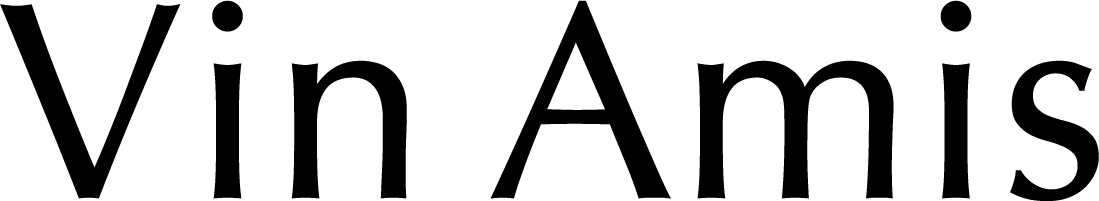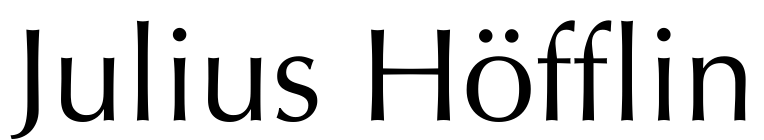
ユリウス・ホフリン
ドイツ/バーデン

国境を越えて醸成された感性
ブルゴーニュのバスティアン・ヴォルバー、ジュラのメゾン・メイナード、そしてニュージーランド・マーティンボローのオラテラ。ユリウス・ホフリンのワインは、こうした多様な土地と造り手たちとの出会いを通じて磨かれてきた。家族のワイナリーで土に触れ、実務を覚えたのち、彼はガイゼンハイム大学に進学。各地の畑に身を置きながら、「ワインをどう造るか」ではなく、「ワインをどう感じるか」という問いに向き合い続けた。耳を澄まし、手を動かし、発酵槽の前で思索を重ねる日々のなかで、ひとつの哲学が彼の中に育っていった。それは、“ブドウが語ることを妨げない”というシンプルでありながら勇気のいる姿勢。醸造はあくまで寄り添うものであり、過度に介入せず、丁寧に見守ることが信条となった。バーデンの火山性土壌で育ったソーヴィニヨン・ブランは、その哲学を体現する一本だ。果実のエネルギーを、酸とミネラルの繊細なヴェールがやさしく包み込み、装飾を排したピュアな味わいが広がる。国境を越えて積み重ねた経験が、いまカイザーストゥールの畑で静かに根を張っている。


既成概念にとらわれない、しなやかな挑戦
ユリウス・ホフリンのアプローチには、常に問いかけるような姿勢がある。「この土地ではこうあるべき」「この品種はこう造るべき」といった既成概念に対して、彼は静かに、しかし確かな手応えで別の可能性を提示する。たとえばピノ・ノワール(シュペートブルグンダー)。ドイツで最も温暖な産地であるバーデン・カイザーストゥールにおいて、彼が重視するのは”酸の表現”。収穫のタイミングは糖度ではなくpHで見極める。フレッシュさを与えるため全房発酵を取り入れつつも、茎のグリーンな印象が出ないよう細やかにコントロールする。”軽さ”ではなく”しなやかさ”を求めたスタイルが、彼のピノ・ノワールに個性を与えている。さらに、気候変動の影響を見据え、ネッビオーロの植樹にも取り組んでいる。「好きな品種であることに加えて、暑さの中でも酸を保てるネッビオーロに挑戦することは、バーデンにとって意味があると思った。年によってはピノ・ノワールには暑すぎる」と語るユリウスの言葉には、情熱と理論、そして未来への責任が同居する。彼の挑戦は派手さを求めない。土と向き合い、風を読み、植生や微生物の声に耳を澄ませながら、自らの感性を信じて“もしも”を積み重ねていくような静かな探究。その歩みは、ワインにとっていちばん自然なかたちを探す旅のようにも見える。

畑は風景ではなく、生態系。アグロフォレストリーという選択
ユリウス・ホフリンにとって「自然とともにあること」は、理念ではなく日常そのものだった。彼の家族は1974年という早い段階から、Bioland認証に則ったオーガニック栽培を実践しており、彼自身もその環境の中で育ってきた。 だが彼は、従来の有機農法に満足することなく、より多様で立体的な畑づくりを目指して、アグロフォレストリー(混農林業)の導入に踏み切った。2023年、自家育成の苗木80本による小さな樹苗畑を立ち上げ、さらに30本のポプラやジューンベリー、キリの若木を畑に植樹。これらの木々は、日陰をつくり、地中深くの水を引き上げ、微生物の活動を促すといった多面的な役割を果たす。こうして彼の畑は、単一作物の場から、多様な命が交わる“小さな生態系”へと変わり始めた。ブドウには火山岩や石灰岩の土壌の個性に加え、複雑な植生や光、湿度のリズムまでもが表れるようになった。ラベルに描かれた木のモチーフは、単なる意匠ではない。それは、家族から受け継いだ自然への敬意と、次の世代へつなぐという意思を象徴するもの。ユリウス・ホフリンのワインには、その静かで揺るぎない哲学が息づいている。
生産者ストーリー
【国際的な同世代との交流により磨かれた唯一無二の感性】
フランス・ブルゴーニュで開かれる試飲会”オー・レ・マン”は、ヴァン・ノエのジョナサン・ピションが主催する注目のイベント。ブルゴーニュを中心にシャンパーニュやジュラなどの注目の生産者が顔をそろえる。この場に、ドイツから参加していたのがヴァーゼンハウス、そしてユリウス・ホフリンだった。彼のワインを口にした瞬間、この場に招かれた理由がはっきりとわかった。バーデンという温暖な地のワインでありながら、そこには明確な冷涼感と静けさ、そして芯のある張り詰めたエネルギーがあった。ブルゴーニュの新星たちのなかでも、しっかりとした存在感を放っていた。試飲会後、あらためてじっくりとテイスティングを重ねたことで、初めに感じた光が確信へと変わった。
ユリウスは、ドイツ・バーデンのカイザーストゥールにある家族経営のワイナリー、ヴァイングート・ホフリンの三代目として生まれた。父マティアスの背中を見て育ちながらも、ワイン造りを職業にすると決めたのは、決して早いタイミングではなかった。両親から「継いでほしい」と言われたことは一度もなく、「好きな道を進めばいい」と背中を押されたという。だからこそ、さまざまな選択肢を模索した末に自ら選んだワインの道は、彼のなかで揺るぎない決意に変わっていった。2015年、ユリウスはドイツの職業訓練制度デュアル・アウスビルドゥングのもと、カイザーストゥールのヴァイングート・ベルヒャーや、ファルツの名門エコノミーラート・レープホルツなどで実務経験を積んだ。その後いったん家業に戻り、畑と醸造の現場を身体で覚えながら、3年にわたって実践的な研修を重ねた。
より深く学びたいという思いから、ガイゼンハイム大学へ進学。在学中には、ブルゴーニュのバスティアン・ヴォルバーや、ジュラのメゾン・メイナードなど、新しい感性を持つ若手生産者たちのもとで研鑽を積んだ。バスティアンの下で働いているときに知り合ったことをきっかけに、ニュージーランドのマーティンボローに渡った。そこでは、ニュージーランドのカルトワインとして知られるドライリヴァーで働いていた6人が、ワイナリーの売却の際に独立し創業したオラテラで経験を積んだ。
実家に戻ったのち、家族のワイナリーでの仕事に携わりながら、彼はこれまで得てきた国際的な視点と現代的な感性を反映させるように、自身のレーベルで独自のワイン造りを始めた。2020年が、その最初のヴィンテージとなった。「家族や友人のワイナリーで働くのは楽しかったし、大きな学びもあった。でも、自分の名前で、自分の責任でワインを造ることが必要だと感じた。全ての意思決定を自分で行い、結果に対する責任をすべて背負う。そうした経験が、ワイン造りをより深く理解するためには不可欠だった」。そう語るユリウスの言葉からは、実直な覚悟がにじみ出ていた。

ヴァイングート・ホフリンは18 haの畑を所有し、1974年以降はBioland(ドイツのオーガニック認証)に準拠した有機栽培を継続している。ピノ・ノワール、ピノ・ブラン、ピノ・グリ、シャルドネ、スーヴィニエ・グリ、ソーヴィニヨン・ブランといった主要品種を栽培し、透明感と複雑味の共存を追求してきた。ユリウスはその中から1 haを自らのプロジェクト用に割り当て、買いブドウには頼らず、自社畑のブドウのみでワインを仕立てている。収量を極限まで抑え、野生酵母による発酵、無濾過、低亜硫酸といった、低介入の手法を用いる。目指すのは、熟成ポテンシャルを備えながら、若いうちからも楽しめるワイン。低いアルコール度数ながらも凝縮感があり、しなやかさと張りのある酸が構造を形づくる。
「ドイツで最も温暖なバーデン・カイザーストゥールという土地で、いちばん大切にしているのは“酸の表現”。収穫のタイミングは糖度ではなくpHで決めている。白はダイレクトプレス、赤は全房発酵を基本にしているけれど、茎のグリーンなニュアンスが出すぎるのは好みじゃない。だからこそ、そこはかなり気をつけている」。そんなバランス感覚が、彼の味わいの奥行きを支えている。また近年、ネッビオーロの植樹にも取り組んでいる。「もともと大好きな品種というのもあるけれど、気候変動の影響で暑い年にはピノ・ノワールが成熟しきれないこともある。そんななかでも酸を保てるネッビオーロは、これからのバーデンにとって意味のある品種だと思っている」。今後はこの個人プロジェクトを、3 ha程度の規模まで拡大していきたいと語る。
さらに彼の取り組みにはもうひとつ、アグロフォレストリー(混農林業)という重要なテーマがある。2023年、彼は自家育成による80本の苗木で樹苗畑を立ち上げ、さらに畑に30本の木を植えた。ポプラやジューンベリー、キリなどの木々は、日陰をつくり、地下水を引き上げ、土中の微生物の活動を活性化させる。これにより畑は単一作物の場から、生態系の一部へと変わりつつある。彼のワインラベルに描かれている木のモチーフは、この哲学の象徴でもある。自然への敬意、そして未来への意志を、静かに語っている。


フランス的な感性と、バーデンの火山性土壌に根ざした誠実なアプローチ。ユリウス・ホフリンのワインは、声高に語らずとも、その一杯がすべてを物語る。静かに、しかし確かな重力をもって、グラスの中に佇んでいる。
DATA
造り手:ユリウス・ホフリン
国/地域:ドイツ/バーデン
栽培面積:1 ha